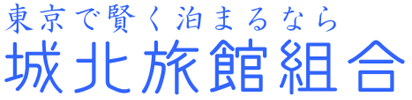 台東エリア宿泊施設一覧
荒川エリア宿泊施設一覧
城北旅館組合の施設を使おう
簡宿のご利用に際して
浅草簡易旅館組合からの歩み
台東エリア宿泊施設一覧
荒川エリア宿泊施設一覧
城北旅館組合の施設を使おう
簡宿のご利用に際して
浅草簡易旅館組合からの歩み
その私達の組合も、昭和20年3月10日、大東亜戦争下米軍の大空襲により、組合員100余軒は一軒残らず一夜で灰燼と化してしまったため、組合員も散り散りとなってしまった。このことは、他の連合会傘下10の支部も焼失の順は違っても皆同様であった。
而し、この長くて苦しかった戦争も、その年の8月15日に終戦となったのであるが、国民の多くは全国的に廃墟となった国土と、敗戦というショックから虚脱状態に落ち入り、さてこれから何をしてよいか分からず、日々雨露を凌ぎ、食糧難のためその日その日の食料を求めることに懸命となっていたのである。
そんな中、組合員の中には何とか再び簡易旅館を再建したいと願う人達もあり、翌年、昭和21年早々より連合会の働きにより、小規模ながら旧軍の施設の払い下げを受けることが決まり、その施設を解体してその木材を再建の資材にと、各地に散った組合員にも呼びかけ、同年3月頃より品川沖のお台場にある旧軍の施設に泊まり込みで解体工事に当たったのである。
その様な頃、焼け跡の街には内外地から復員してくる人達も段々と増えていたが、帰って来ても住む家もなく、働きたくても職もない状態、又、戦災により家を失って同じく行き場のない人達も多く、この人達は少しでも雨露の凌げるところとして、上野駅の地下道一帯を始め、都心の各駅を中心にネグラとして集まり、着のみ着のままの野宿であったため、保健衛生は勿論のこと、中には栄養失調者も多く、駅を利用する人達からも目に余る状態となり、占領軍総司令部の強い圧力により、稼働能力のある者は宿泊施設に保護するようにとのことから、東京都は困惑して私達の連合会に協力を求めてきたのであった。
前述の通り、私達の連合会は組合再建のため、お台場での旧軍の施設の解体工事に傘下各組合の協力の下、積極的に取り組んでいる最中であったが、この申し入れを組合全体の復興への足掛かりにと東京都よりの協力申し入れに応じ、都内11ヶ所の各支部へ呼びかけ、それぞれの各支部地内の焼け跡に旧軍の野戦用の天幕の払い下げを受け、前述の住むに家なき復員者、戦災者の受け入れのために昭和21年秋より暮れにかけ天幕の施設を設置することになったのである。
天幕一張りの収容人員は約20名以上、私達の組合では20張りの天幕を組合地内6〜7ヶ所に設け、行政側が上野駅一帯を中心に野宿している人達をトラックに乗せて運び、当初は400名以上の人達を天幕の施設に収容したのである。
(この施設は東京都民生局委託施設「厚生館」と称した。又、当初は無料であったがその後有料となり、更に委託契約も切れて民間経営となった。)
戦災の焼野原にこの様な天幕が集中して多数設けられ、400名以上の人達が生活し働きに出る足場となってくると行き交う人も繁くなり、焼け跡の中にも生活に活気が甦ってきたのである。
この様な生活の活気と焼け跡の賑わいを見た組合員の中には、一日でも早く自分も元の場所に帰りたいとの思いが強まり、小さくともバラックながら元の場所に家を建てる人、また小さな簡易旅館を自力で再建する人など、その後、昭和23年頃までに先の天幕の施設とは別個に組合地内に20軒以上の簡易旅館が再建され、更に昭和25年の朝鮮戦争による戦争景気から働く人達の仕事も増えて来たことにより、活気が活気を呼び、年々簡易旅館としての施設も再建されると更に多くの人達が集まり、昭和28年頃には小規模な簡易旅館を含め100軒を数えるまでになり、宿泊人数も約6,000人以上、戦前以上の旅館街が復興したのである。
然るにこの間、私達の簡易旅館を利用する人達の仕事は、日雇い労働その他小商工業者等で主に低所得者が多く、その上、当時は未だ戦後の混乱と経済の低迷も続き、その日暮らしの苦しい生活の人達や家族持ちの人達も多く、生活保護対象者も多かったのであるが、当時は行政側の充分な対応もなく、どうにもならない状態であった。
このため、私達の地区の簡易旅館業者は、営業は営業として、行政側が対応出来なければこれは地区の問題でもあるとして、組合が中心となり地区の関係業者、町会等との協力の下、多面的な福祉事業を計画し実行するなど、積極的に協力してきたのである。
この当時の私達の組合リーダー達は、自分の簡易旅館の再建に努力するばかりではなく、組合全体の復興と地区の復興をも併せ願い、相互の連絡を密に、先輩との纏まりもこれ又堅く、その力が結集していればこそ戦前以上の簡易旅館街として復興することが出来たのである。又、その力はその後も続き、幾多の変遷を乗り越えて今日に至る50年余年の長い年月を支えてきたのであった。
2000年3月31日
松村 幸雄 記